雨がシトシトと続く梅雨。
なんとなく気分が落ちる季節ですが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。
梅雨は釣りに行く方と行かない方に分かれます。
総合的には雨の日は釣りに行かない、という方の方が多くなります。
釣りものによっては雨だととにかく大変なことになるものもあるでしょう。
また雨の日に辛い思いをして釣りをする価値があるのか。
苦行の果てに、釣れるのか。
と疑問を持たれている方もいらっしゃるかと思います。
梅雨の時期、魚によっては一年の中で最高のシーズンとなるものもあります。
傾向的には最高サイズを出す時期というよりは最高数釣れる時期になることが多いです。
今回は梅雨がもたらす釣りへの影響について解説いたします。
この記事の内容はYouTubeでご覧いただけます
梅雨の時期は釣れるのか、釣れないのか
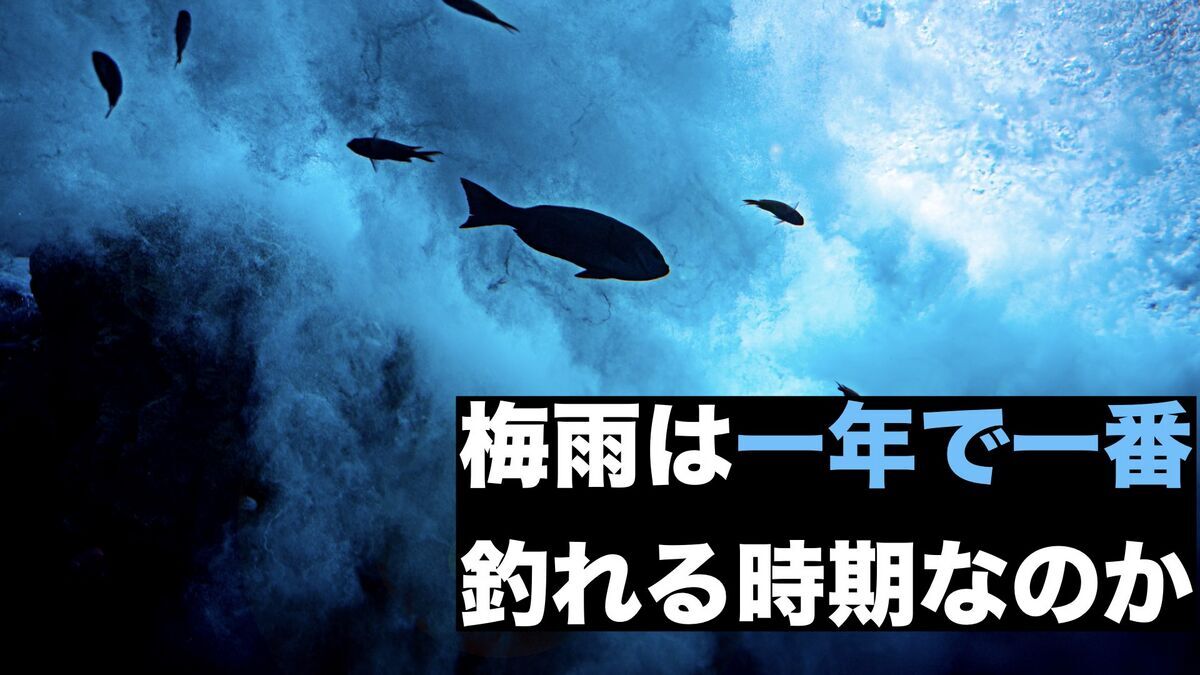
梅雨の時期に釣れるかどうか、の前に注意しなければならないのは危険性について。
長く雨が降った影響で河川の水が増えたり、土砂災害の危険もあります。
こういった危険なところが通常より多いというのは理解しておかねばなりません。
特に河川においては自分のいるところでは雨が降っていない、
または弱くても上流では降っていると急に水量が多くなることがあります。
時にダムが放水を開始すると、こちらも一気に水量が増します。
地域の情報、気象予報は常に確認するようにしましょう。
梅雨というのは多くの場合、釣りにプラスになります。
というのも光量が少ないから見切られにくい
適度な雨でプレッシャーがかかりにくい
気圧によって魚が浮きやすい
といった要素があります。
ただし、梅雨の雨っぽい状態の話で毎週台風が接近するような状態
大雨が定期的に起こり、河川が増水しゴミが海に流れ濁るという状態は良いものではありません。
梅雨っぽいじめっとした感じの状態が釣りにとってはプラスになりやすいのです。
もちろんプラス要素だけではなくマイナス要素もあります。
それでは順にご紹介いたします。
光量
雨や曇りでは晴れに比べれなかなり光量が落ちます。
光量が落ちると人間も同じですが魚も視界が悪くなります。
そのためルアーや餌といったものが鮮明には映らなくなるため、晴れの日よりは見切られにくくなります。
ちなみに晴れで水面ギラギラの状態。
この状態でルアーが1m程度潜っていると鮮明に魚に見えています。
逆に水面ギラギラに近づけるほどにルアーのシルエットはボケてきます。
晴れの日で凪の日ほど水面直下やトップが見切られにくくなります。
波が立ってしまっている状態では水面直下やトップではルアーの存在感が消えてしまうので沈める必要があります。
深いポイントを狙う釣りではあまり曇りや雨といった要素は関係ありません。
場所や潮によっても異なりますが水深50mあたりからかなり暗くなってきます。
光量が少ないと釣れやすい、というのは朝まずめ、夕まずめでも同じことです。
また晴れの日は影が落ちやすくなります。
人間が海辺に立って太陽を背負った状態であればその影がしっかりと海の中へと落ちていきます。
魚は結構陸を見ているものです。
見てるとはいってもよく見えているわけではありません。
しかし我々人間より警戒心が高いため、危険か安全かはわからないが何かが来た時には身を隠します。
逆に飼い慣らした魚なら人の影を見てよってきます。
それだけ魚は水の外を認識しているということです。
雨
雨はノイズ、といっても良いかもしれません。
海の中でも海面を叩く雨の音はしっかり伝わり
それが陸地の音をかき消してくれる効果があります。
人間の話し声、歩く音、キャストする音などは雨で誤魔化してくれます。
といっても効果は抜群だ!というわけではなく気休め程度とも言われています。
豪雨のように凄まじい音であれば完全にかき消すことができるかもしれませんが今度はそれのせいで魚が出てこなくなるとも考えられます。
雨がもたらすマイナス面では海水の塩分濃度の低下。
局所的豪雨が長時間続くといった場合を除き、塩分濃度の低下は海面の薄いところのみです。
ただうっすらと塩分濃度は低下するらしく、塩分濃度に敏感なイカは影響の少ないところに行くと言われています。
塩分濃度以外には水温の低下。
夏の時期、シイラは水温が高い方が活性が高くなります。
そのため長く雨が続いたりするとこれまで好調だったシイラが釣れなくなったりします。
高水温を好む魚にとっては長い雨は厳しいかもしれません。
また年によって冷夏と言われるような時になると6月本来の水温にならず、魚の活性が上がってこないということもあります。
また春のパターンを引きずるということもあります。
釣りをするエリアの水温をよく観察して、パターンを研究する必要があるでしょう。
低気圧
低気圧は魚の浮袋に影響を与え、魚を浮きやすくし、活性を上げると言われています。
ただし浮袋を持たない魚
ヒラメ、サワラといったものもいるので全てに共通しているわけではありません。
浮袋に関しては小さい魚ほど影響を受けやすい
つまりベイトは浮きやすい、それを食う魚も気持ち浮きやすい
ということは全体的に魚が浮きやすい、と考えられています。
諸説ありますが晴れの日より曇りの日の方がナブラが立ちやすい、ボイルが見えるという報告もあります。
梅雨前線の位置によって海水がかき混ぜられ状態が良くなったり、春の低水温から水温を上げてくれることがあるので活性につながることもあります。
ただ、これに関しては先ほど紹介した雨の要素でのマイナス面もあるので一概にプラスということはできないでしょう。
濁り
梅雨時期は濁りが起きやすくなります。
河川の増水といったものが一般的ですがこれらを好む魚にはかなりプラスになります。
濁りを好む魚
クロダイ
シーバス
マゴチ
これらは河口付近に生息しています。
適度な水量と濁りが流れている場所ならこれとないチャンスになるでしょう。
クロダイ、シーバス、マゴチの最盛期が梅雨時期かもしれません。
水温や雨の量も関係して梅雨時期はトップより巻き
梅雨明けからトップのシーズンといった場所が多いようです。
ちなみにシーバスは濁っている方が釣りやすくなることが多いですがヒラスズキになると濁っていないところの方が釣れます。
春から梅雨にかけて日中に潮が大きく動くためシーバスのデイゲームがいい季節。
磯マルも磯ヒラも良いシーズンです。
よくあるのがヒラスズキを狙っているがマルスズキばかり釣れる。
このように釣れるポイントが同じというエリアもあります。
こういった場合、ヒラスズキだけに絞りたいのであれば濁りがない磯に行く、という方法がおすすめです。
完全に分離できるわけではありませんがお困りの際、ご参考になれば幸いです。
今回は梅雨がもたらす影響についてご紹介しました。
多くの釣り人がいうのが
晴天 ベタ凪は釣れない
まさにその通りだと思います。
理由は様々ありますが魚と釣りという行為の相性が悪くなる天候なのではないでしょうか。
その点、雨で濡れたり、危険が伴ったりとありますが梅雨時期の方が釣れやすくなります。
豪雨では釣りが厳しくなりますし、落雷は絶対に無理です。
無理な釣行はなさらず、今回も安全に行ってらっしゃいませ。