青物用ルアーといえばメタルジグ、またはトップウォーター系ルアーであるポッパー、ダイビングペンシルが主流です。
近年ではこれらに加え汎用性の高いシンキングペンシルも大人気。
シンキングペンシルは飛距離も出る、レンジをコントロールできる、
鉛の塊ではなくより魚に近いプラグである
メタルジグとプラグのハイブリッドルアーとも言えるでしょう。
ルアーフィッシングの代表といえばミノー。
釣りをしたことがない方でもルアーはどんなものか、と聞けば多くの方はミノーっぽいシルエットを想像します。
しかし青物ルアーでミノーはないわけではありませんが主力というよりは変化球要員的な扱いになっています。
水面直下をぶりぶり泳ぐミノーが主役になっても良さそうな釣りですが、トップやメタルジグにその座を開け渡しているのはなぜでしょう。
今回は青物ルアーでミノーが主役ではない理由について解説いたします。
この記事の内容はYouTubeでご覧いただけます。
なぜ青物ルアーの主役はミノーではないのか
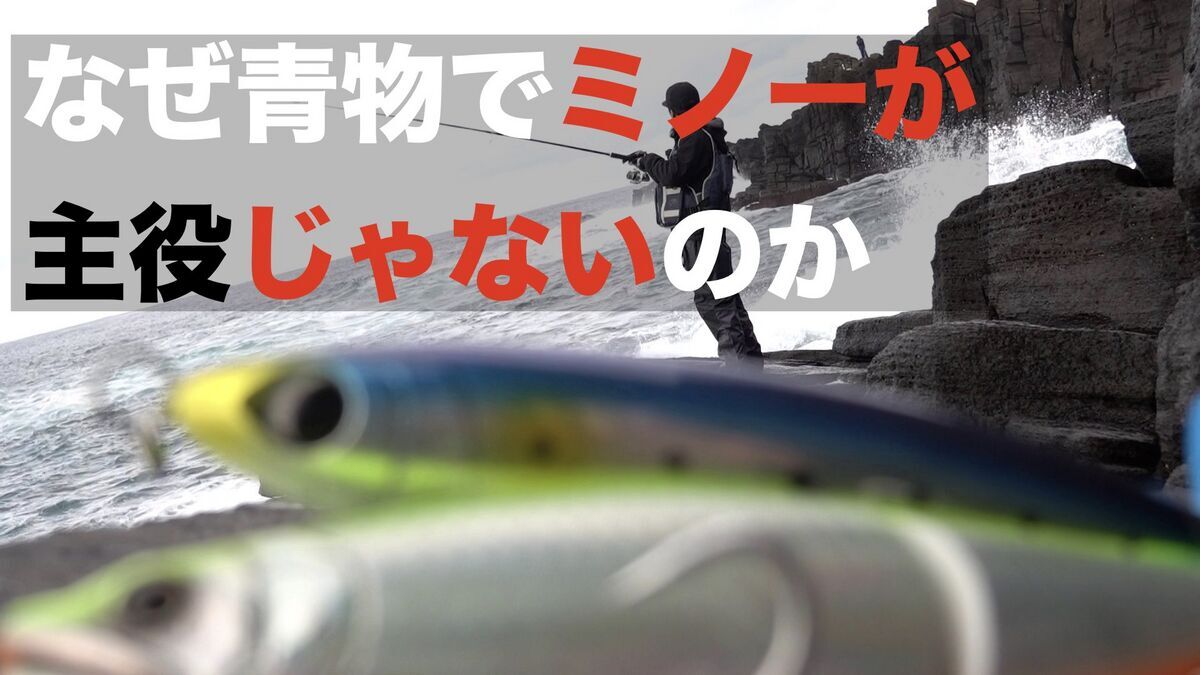
まず青物の性質から見ていきましょう。
青物が他の魚と大きく異なるのは遊泳速度。
青物といってもいろいろいますが基本的には青物と言われる魚は他の魚に比べると圧倒的スピードを誇ります。
そのため基本的にルアーの巻く速度も早くなってきます。
巻く速度は時によって「本当にこれで大丈夫なのか」
と思うほど
ハンドルが壊れるんじゃないか
と思うほどの速度が必要になることもあります。
完全に不要、というわけではありませんがゆっくり、じっくりルアーを見せて釣る
ゆっくり見せたのちにアクションをかませ、リアクションバイトを狙う
という多くのルアーで基本とされる釣りではなく、総合的に勢いが必要になる釣りです。
繊細な釣り、というよりは豪快な釣りという印象が強いかもしれません。
こういった傾向からあえてミノーである必要はない
という点が出てきます。
ルアー界の中心であるミノーがあまり必要ではない理由は他にもあります。
飛距離が出ない
青物釣る上で圧倒的有利になる要素
それは飛距離。
飛ばせば釣れるという脳筋思考が絶対的釣果を生むわけではありませんが飛距離が出た方が釣れる可能性は高くなります。
メタルジグはシルエットを小型化
そして金属の塊であるため小型化しても重さがあります。
シンキングペンシルもこれに近く、
プラグではありますが内部に錘がガッツリ詰まっており
重さがありながら小型化することができます。
メタルジグ、シンキングペンシルはいわゆる固定重心タイプ。
ただ巻きすると似たような泳ぎ方をします。
次にダイビングペンシル、ポッパー
これは大型化することで重さが出る
大型でなくてもフォルムが丸っこいため、内部の移動重心システムを大型化でき飛ばすことができます。
ミノーに関しては大型であったとしても丸っこいものは少なく、丸っこくなるとミノーではなくなってしまう
ミノーは基本的に細長いルアーです。
そのためダイビングペンシルやポッパーとは異なり、内部に余裕がなく、大型のシステムを搭載することができません。
ではミノーをメタルジグ、シンキングペンシルのように固定重心にすればどうか。
現在、多くの青物用ミノーはこの方式が採用されています。
ただ飛距離に特化するとミノーではなくなってしまうという問題を抱えてみます。
後ほど紹介いたしますがアクションを維持することが難しくなるという問題が出てきます。
またミノーという形状と固定重心の相性もあまり良いものではありません。
飛距離が出るルアーというのは基本的には飛行姿勢が綺麗なものです。
しっかりお尻から飛んでいきます。
メタルジグ、シンキングペンシルは固定重心ですがバランスがうまく取れており、ミスらな限りお尻から飛ぶようにできています。
ダイビングペンシル、ポッパー、も移動重心システムが働くことでお尻からしっかり飛びます。
またウッドルアーは固定重心ですがこちらも綺麗な飛行姿勢で飛びます。
ミノーは細長くなりやすい
リップが大きくなりやすい
といった要因から空気抵抗を受けやすくなります。
他の青物ルアーと比較してみると流線型から少し離れてしまいます。
無理ではありませんがキャストにはかなりコツが必要になり、ジグやシンペンと同じ重さであったとしてもなかなか飛ばすことが難しいのがミノーです。
固定重心のミノーは回転しがちです。
さらにこのようなボディバランスから大型のフックを搭載しにくいという問題もあります。
ただでさえ空気抵抗が複雑で、そこから重さのある大型フックをつけるとバランスを取るというのは無理ではないかもしれませんが困難です。
メタルジグ、シンキングペンシル、ダイビングペンシル、ポッパー
これらは釣り人が行うアクションで動きが変わります。
またアクションをさせないと本来の性能を100%発揮することができません。
しかしミノーやバイブレーションはアクションさせる
というよりは誰でも簡単ただ巻きで釣れる、というルアーです。
こういった点からミノーを作る上では最重要項目であり、飛距離のためにこれがなくなるとミノーとはいえなくなるのです。
アクション
ただ巻きでぶりぶり泳いで魚を誘うミノー。
どうしたこういった動きをするのか
それはミノーのフォルム、リップの形状、そして適度なルアーの重さによるものです。
ルアーが重くなればなるほど、ただ巻いた程度では小刻みに振動する
ウォブリング、ローリングはしにくくなります。
軽いもの、短いものほどブルブルと小刻みに動きやすくなるのはなんとなくイメージできるかと思います。
青物用のミノーを作る上で前提としてこのようなアクションを維持する
飛距離を出そう
と思ったらすごい性能のシステムを搭載するか固定重心である必要があります。
現代技術において爆発的な飛距離を出せるシステムはあります。
さらにこれに合わせてルアーの飛行姿勢を調整することで尻上がりで飛ぶ
飛行機の羽が生む浮力、これの応用を用いたものが出ています。
しかしこういったものがコスト的に優れているか、と言われると現在ではなんともいえないところではあります。
ではミノー本体に重さを持たせ、固定重心にするとします。
そうすると重さがミノーとしての動きを悪くします。
重いから動きが悪い
となればどうするか。
解決方法としては巻き速度を早くすることで入力を大きくし、ミノーを泳がせる方法があります。
普通のミノーが引き波といった流れに引っ張られると通常よりブルブル泳ぐことがあります。
これと同じように巻く速度を早くすると重いミノーでもしっかり泳ぐようになります。
しかし遅い巻きでは泳がなくなるという欠点があります。
全てではありませんが現在売られている青物用ミノーでは最低速度的なものがあります。
その速度を下回ると泳がなかったり、横に振られてどこかに行ってしまうことがあります。
これは大型、重くなれば最低速度も速くなります。
お使いのミノーがなんか上手く泳がない、という時にはもっと速く巻いてみてください。
逆にあまり多くないですが早すぎて泳がないミノーもあります。
通常のミノーは低速から高速まで対応していますがヘビーウェイトミノーではこういった適正速度といったものが出てしまいます。
使い手、状況を選ばないミノーですがこれに関してはかなり取り扱いが繊細なルアーになってきます。
今回は青物ルアーにおけるミノーの事情について解説いたしました。
青物狙いではマイナス面がやや多いミノーですが状況によってはミノーが最強、
ミノーでしか釣れないという場面もあります。
シイラにおいては結構こういった場面が多い釣りです。
釣りに行く際、一つは入れておきたいところ。
最近青物ミノーで評価が高いのは
シマノ ロックジャーク
ジャクソン ピンテール
これらは釣具屋さん、ネットでもかなり売れており、評判のいいルアーです。
概要欄に貼ってありますのでよろしければ一度使ってみてください。